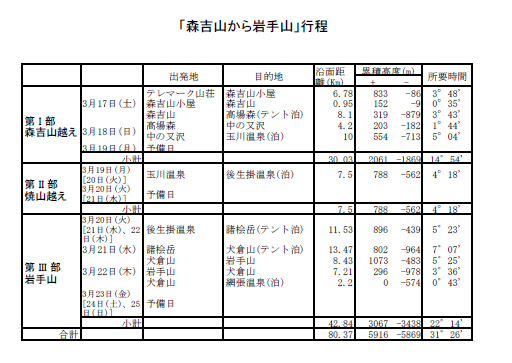「岳人」11月号の記事がちょっと話題になった。一部に誤解があるようである。私は竹内君の記事を批判したわけではなく、太田君も批判はしていない。ただ、一般に、「…の父」という大げさな称号は止めた方がいいと考えているだけである。太田君も同じような考えだと思える。山には「英雄」はいらんのだ。京都の登山界は大きく分けて二つの流れがあるとしたが、優劣は論じていない。基本的に、山は好きなように登ればよい。ただ、北山に関しては、「北山の会」が主体的に関与したいと考えている。
マスコミは英雄をつくりたがる。森本次男を英雄視すると言えば大げさだが、「北山の父」とするのは一種の偶像視である。英雄視も偶像視も似たようなものだ。本人が望んだわけではなかろうが、取り巻き、あるいは英雄待望の世論(マスコミ)というものが作用していたかもしれない。
アウトドアの世界で、現代のつくられた英雄の典型は植村直己であろう。植村には何の恨みもない。植村を称賛したい人はすればよい。だが、私から見れば、植村は近代アルピニズムの範疇からは完全に外れた存在である。近代アルピニズムの根底思想はパイオニアワークとアマチュアリズムである。
ヒマラヤの処女峰時代が終わって、登山は変質した。即ち、スポーツ化と商業主義の台頭である。処女峰がなくなったので、次に狙うのはバリエーションルート、アルパインスタイル、無酸素といったよりスポーツ的傾向であった。また、テレビの影響で商業主義が強く表れた。登山の職業化である。これはアマチュアリズムの崩壊を意味する。登山を続けることでマスコミの脚光を浴び、生計をたてるという人々が現れた。植村がその嚆矢である。植村はテレビで持てはやされ、テレビのために死んだ。
植村に没後、国民栄誉賞が与えられた。どういう賞かよくわからない。植村は死んでいるから、それを望んだかどうかわからない。だが、生きていたとして、それを拒んだとは考えにくい。英雄視された男にふさわしい栄誉というべきか。
ヨーロッパにラインホルト・メスナ―という登山家がいる。8000m14座にすべて登った男である。毀誉褒貶激しいと聞くが、私はメスナ―を秘かに尊敬している。オリンピックの“愚物”サマランチが特別メダルをやる、と言ったとき、メスナ―は何と応えたか。「登山はスポーツではないからいらん」だったのだ。世俗を嫌うこの一言は、十分に傾聴すべき価値がある。
メスナ―は少し遅れて世に出た登山家である。処女峰時代は終わっていた。だから、無酸素とか、単独登攀というスポーツ的登山に向かわざるを得なった。そのメスナ―にして、「登山はスポーツではない」と言わしめたのは何か。私はそこに、ヨーロッパに深く根付いた近代アルピニズムの矜持を見る思いがする。植村との違い、日本とヨーロッパの思考の違いといったものも感じてしまうのだ。
余談だが、「ヒマラヤ 運命の山」というメスナ―を主人公にした映画を観た。特にメスナ―を英雄視していないところがよかった。ナンガパルバットでの隊長の指揮を無視した行動、弟ギュンターを死なせたことなど、淡々と描かれていた。
友人の前芝茂人君(同志社山岳会、日本山岳会)からスイス山岳会についての知見を得ているので紹介する。登山先進地のヨーロッパと日本の、登山についての思考の違いを痛感する。前芝君は小学館でスイス山岳研究財団が出す「マウンテン・ワールド」の日本版編集をしていたことがある。1982年にスイスを訪ね、同会幹部のA・エグラーと打ち合わせをしたとき、エグラーはこう語ったという。「1960年代でスイス山岳会の役目は終わった。『マウンテン・ワールド』も1969年までで廃刊したのだ」。1960年はスイス隊の二つ目の8000m峰、ダウラギリ登頂の年代を意味するのかもしれない。時代の変化を認識している。前芝は一つの見識と思ったと、いまになって思い返す。
スイスの貴族ド・ソシュールがモンブランに登って近代アルピニズムに火をつけたのは1787年、難攻不落のマッターホルンがイギリス人、エドワード・ウインパーによって登られたのが1865年である。この間に、ヨーロッパ各国で登山活動の花が開いた。
一方、日本において、ウオルター・ウエストンの前穂高登頂(1893年)を近代アルピニズムの開花とするなら、ド・ソシュールとの間に約100年の差がある。列強入りを目指して欧米の技術、文化を取り入れようとしていた明治期の日本人は、ハイカラな登山にもいち早く目をつけた。1905年には日本山岳会が興り、1956年にはヒマラヤのジャイアンツ、マナスル初登頂の栄誉を掌中に収めるに至った。恐らく、関連する人口、その実績において、日本は世界を代表する登山国であろう。だが、昨今の登山界の変貌に対処する姿勢には彼我に著しい違いが見られる。それはヨーロッパと日本の、近代アルピニズム100年の差によものではないだろうか。メスナ―の登山感にも、それを強く感じるのである。
処女峰時代が終わって、近代アルピニズムは終焉した。日本においてはマナスル登頂で一つの時代が終わったのである。だが、日本の登山界にはその認識がない。無定見にスポーツ化、商業化を受け入れ、近年は「山の日」制定などの茶番に血道をあげている。スポーツ化、商業化が悪である、と決めつけるわけではない。山は好きなように登ればよい。だが、近代アルピニズムを標榜してきた山岳会にあっては、そこに一線を画してほしいと思うだけである。日本国は敗戦という一つの時代を区切りに、民主国家として新しく生きることを世界に宣言した。登山界はそれをしていない。
話が逸れた。山の世界に英雄はいらないが本筋であった。「父」もいらない。商業主義は英雄を待望する。そこに登山家が陥る危ない罠がある。北山の山岳史跡公園構想は、公園化して標識やベンチを設置しようとするものではない。北山荘周辺が私有地であることに一抹の不安を感じているのである。所有者が代わると、北山荘がどうなるかわからない。府教委に買ってもらうか、我々が買うか、一切の開発を断ち、現状維持できる道を模索したい。
(2011年10月27日、四手井 靖彦)